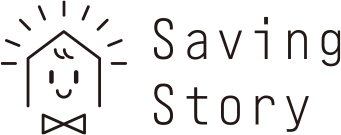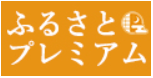2015年頃から盛り上がりを見せている、ふるさと納税。制度がどんどん改善されていることもあって、参加している人も増えているみたいだけれど…本当にお得なの?私でもできる?今回はふるさと納税のデメリット・メリット、使いこなし方、ざっくばらんに紹介します!
目次
1.ふるさと納税ってそもそも何?

ふるさと納税とは、地方自治体へ寄付をすることで、地方創生に参加できる制度のことを言います。
ふるさと納税が他の募金や支援金と異なるのは、寄付をすると自治体独自の返礼品がもらえる、という点です。
例えば、返礼品にはこのようなものがあります。
| 佐賀牛赤身の極みランプステーキ500g | |
 |
寄付金額:10,000円 市場価格:8,000円 寄付先:佐賀県唐津市 |
そうですね。このように返礼品はその地域の特産品や名産品などを中心に用意されています。
自治体側は地域の宣伝ができて、参加者は返礼品を楽しめるという、双方にとってメリットの大きい制度です。
返礼品はモノに限らず、航空券や旅行券などの体験が選べることも!
さらに、参加者は確定申告をすることにより、いくら寄付しても負担がなんと2000円で済むようになります。
これは2000円の超過分が全額、所得税と住民税から還付・控除されるというふるさと納税の仕組みによるものです。
超過分は寄付した自治体の支援金として、自治体に届けられます。
つまり、参加者が住む自治体に納めていた住民税を、自分の支援したい地域に代わりに納めることができるのです。
だからふるさと”納税”っていうんですね!
そうですね。
メリットが目立つふるさと納税ですが、デメリットといえる点はいくつかあります。
しかし、どのデメリットも、正しく理解すれば解決することができます。
2.ふるさと納税のメリットデメリット9選
下の表は、世間や他のサイトで指摘されがちなデメリットとメリットをまとめた一覧表です。
| デメリット5選 | メリット4選 |
これらのデメリットは間違ってはいませんが、必ずしもデメリットとは言えない場合もあります。
また、どのデメリットも、適切にふるさと納税すれば解決することができます。
次の章では、デメリットの詳しい説明とその解決策を見ていきましょう。
3.ふるさと納税のデメリット5選

デメリット1.節税になるわけではない
ふるさと納税は、厳密にいうと節税にはなりません。
というのも、ふるさと納税は、
「本来住んでいる地域と国に払うはずの税金を、代わりに出身地などの地方自治体に寄付することができる」
制度だからです。
そのため、払うべき税金の総額は減っていません。
むしろ、自己負担金2,000円の分、出費が増えてしまっていますよね?
しかし、ふるさと納税は節約になります。
というのも、寄付した自治体からお礼の品をもらうことができるからです。
2018年現在、ふるさと納税に参加している自治体はとても多く、お礼の品もバラエティ豊富になっています。
そのため、多くの人が欲しかったお礼の品を見つけることができるでしょう。
それを寄付のお礼としてもらうことができれば、それを買うためにするはずだった出費を抑えることができますよね?
つまり、ふるさと納税をすることで、
「お礼の品を買うためにするはずだった出費ー自己負担金2,000円」
の金額分、節約することができます。
ビール1ケースや、佐賀牛1㎏、レトルトカレー50食などの、ふるさと納税で定番のお礼の品を詳しく見たい方は、こちらの記事がおすすめです。
デメリット2.いくらでも無限に寄付できるわけではない
記事の初めにいくら寄付しても負担が2000円で済むとお伝えしましたが、寄付できる額には上限があります。
上限は人によって異なり、上限額は収入や家族構成、さらに会社員なのか個人事業主なのか、なども関係してきます。
また、上限額の計算で使用されるのは、寄付した年の1~12月の収入(ボーナス含む)なので、
なんてことにも注意が必要です。
自分がどれだけ寄付できるのか今すぐ知りたい!という方は、こちらのシュミレーションをご利用ください。
こちらのシュミレーションは、昨年の年収から計算しています。
そのため、今年大幅に収入が増えた方、個人事業主で収入が一定ではない方は、
こちらの記事で紹介している年収別の上限額表を参考に、自分の上限額を把握しましょう。
参考記事:【ふるさと納税】年収200万~1,000万円の控除上限額とおすすめ返礼品
また、上限を超えた分は自己負担となってしまうので、少なめに見積もっておくと良いでしょう。
という方も、いるのではないでしょうか?
そんなアナタにおススメなのが、さとふるの寄付額管理サービスです。
無料会員登録をすることで、自分が今年いくら寄付したかを管理してくれます。

出典:さとふる
無料会員登録は約3分で完了しますので、ちょこっと暇な時間にパパっと済ませてしまいましょう。
デメリット3.家計を一時的に圧迫
ふるさと納税は最大限に控除を利用することにより、自己負担金2000円という破格で様々なお礼品を楽しむことができます。
しかし、住民税の控除は翌年6月以降と決まっています。
例えば2018年の3月に2万円を寄付しても、2019年の6月以降にならないと、1万8000円は返ってこないのです。
6月から来年の5月までの1年間、毎月、住民税が安くなるという形で控除になります。
いつの間にか返ってきていた、という感覚なので、一時的な出費は避けられません。
そのため、貯金するつもりだったお金でふるさと納税すると、
実質的に貯金にもなり、家計を圧迫せずにお礼の品をもらうこともできるので、おすすめです!
デメリット4.返礼品がすぐ来るとは限らない
ふるさと納税を各自治体のページから行った場合、礼品の発送のタイミングは自治体ごとに異なります。
発送までの所要期間はサイトに記されていることが多いですが、年末など申し込みが立て込んでいる場合には、連絡もなく発送が遅れてしまうこともしばしばあるそうです。
仕方がないとはいえ、少し不安になってしまいますよね。そんな時には、発送完了メールを送ってくれる「さとふる」を利用するのが安心です。
発送目安も細かく記載がありますし、実際にその通りに届くかどうかは口コミを参照すればわかってしまいます!
あらかじめわかっていれば、欲しいタイミングに間に合うように申し込むことができて、嬉しいですよね。
また、冷凍で届くことが多く、賞味期限が長いものが多いので、余裕をもって早めに頼んでしまうと良いと思います!
デメリット5.ふるさと納税は手続きが複雑?
こう思っている方も少なくないのではないでしょうか?
しかし、仕組さえわかってしまえば、そこまでめんどくさい手続きはありません。
ここでは、ふるさと納税の手続きを「寄付の申し込み」と「ワンストップ特例制度と確定申告」の二つにわけて解説していきます。
デメリット5-1.寄付の申し込みはめんどくさい?
ふるさと納税は、地方自治体の特設サイトか、ふるさと納税のポータルサイトから申し込むことができます。
お申し込み自体は、寄付先(返礼品)を選ぶだけなので、どこから申し込んでも10分もかかりません。
寄付先を選ぶにあたっては、たくさんの自治体が登録しており、品揃えが豊富なポータルサイトがおすすめです。
その中でも、特におすすめの3つのポータルサイトをここでは紹介します。
| 順位 | サイト名 | おすすめポイント |
|
CMでもおなじみ!認知度、利用意向がNo.1のサイトです。 申し込みから決済までWeb上で簡単に! 控除上限額の計算もスムーズに行うことができます。 |
||
|
|
おすすめ返礼品を自治体毎に紹介! |
|
|
|
ジェラートピケやメゾンドリーファーのボディケア用品など、 女性に嬉しい美容品の返礼品をさがすならこちら! |
表に書いてあるようにサイトによって様々な強みがありますが、
というあなたに俄然オススメなのがさとふるです。
何故かというと、見やすく、返礼品のバラエティ豊富で、手続きも簡単だからです。
なので、まずはここで探して、欲しいものがなかったら他で探すという流れが良いと思います。
ちなみに、さとふるであれば会員登録を含めて5分で申し込みが完了します。
申し込みが完了してしばらくすると返礼品が届きます。
返礼品のタイミングは自治体によって様々なので、「〇月×日に欲しい!」という希望がある方は発送時期の欄を必ず確認しましょう。
デメリット5-2.ワンストップ特例制度と確定申告がわからない
「ワンストップ特例」とは、サラリーマンが会社に申請することで確定申告をしなくても税金の控除を受けることができるという制度です。
確定申告に慣れない人にとっては朗報のワンストップ特例制度ですが、利用するには条件があります。
|
①確定申告の必要がない人 ②ふるさと納税の納付自治体が5箇所以内の人 ③納税を行った翌年の1月10日までに書類を提出 |
この3つをクリアするのって、けっこう大変なんです…。
特に③これは各自治体に一部ずつ用意して提出しなければなりません。
仮に5箇所に提出したとして、1箇所でも不備があって1月10日に間に合わない場合には、
確定申告に行かなければなりません。
とはいっても、ふるさと納税のみの確定申告はそこまで大変ではないので、書類を用意する手間を考えれば、初めから確定申告でもいいのではないかと思います。
なお、「さとふる」内には、4ステップで確定申告のPDFを作成できるページがあります。
そちらを利用してみるのも一つの手です。
4.ふるさと納税のメリット4選

メリット1.豪華な返礼品がもらえる
たった2,000円の自己負担金で、ステーキや鰻などの豪華な返礼品をもらうことができます。
お得な返礼品を選ぶことを意識すれば、
寄付金額10,000円につき約5,000~10,000円相当の返礼品をもらうことも可能です。
下の記事では、誰でももらうことができるお得な返礼品ランキングを紹介しているので、ぜひご覧ください!
メリット2.自分の故郷に限らず応援したい自治体を選べる
ふるさと納税という名前はついていますが、自治体は自分の出身地以外も自由に選ぶことができます。
お礼品から選んでもよし、応援したい地域から選んでもよし、寄付金の用途から選んでもよし。
メリット3.被災地の復興・復旧に役立てることができる
さとふる内に、「ふるさと納税の使い道」というページがあります。そこに災害支援・復興の項目があり、支援したい地域を選んで寄付することができます。
また寄付金の使い道も明記されています。
メリット4.寄付金の用途を指定できるので、自分のお金がどこに行くか見えて安心
例えば災害支援のために募金をしても、それがどこに使われているか分からない…と不安になることはありませんか。
「ふるさと納税の使い道」では、災害支援や地域復興以外にも、教育、医療、スポーツ・文化支援などの幅広い用途から指定することができます。
5.返礼品がなくなるかもしれないデメリット
ここまではふるさと納税の制度に関するメリットデメリットを紹介してきましたが、
ここからは、返礼品に焦点をあててメリットデメリットを紹介したいと思います。
さて、まずは、「返礼品はなくなるかもしれない」というデメリットです。
サイトで見つけた魅力的な返礼品や、一度もらって気に入った返礼品。
なんて呑気に思っていると、頼めなくなってしまうかもしれないんです!
頼めなくなる原因は3つあります。
①品切れ
②季節限定
③行政からの指導
①と②は説明する必要がないですね。
「佐賀牛切り落とし1㎏」などのポータルサイト人気ランキングの上位の返礼品は①、
「シャインマスカット 約1.5kg」などの収穫時期が限られている果物は②に注意が必要です。
| 佐賀牛切り落とし1㎏ | |
 |
寄付金額:10,000円 市場価格:5,000~7,500円 寄付先:佐賀県嬉野市 |
| 【新鮮果実】人気のシャインマスカット 約1.5kg 紀州グルメ市場 | |
 |
寄付金額:10,000円 市場価格:3,730~4,980円 寄付先:和歌山県湯浅町 |
さて、③行政からの指導とはどういうことでしょうか?
実は、2016~2017年ごろに、ふるさと納税という制度が普及してきたことによって、自治体間の寄付の獲得競争が過熱していました。
その結果、返礼品のお得さとバラエティを過剰に充実させた一部の自治体が寄付を大量に集めている状態になってしまいました。
しかし、ふるさと納税の趣旨は、都心に集中しすぎた税金を地方に分散させることなので、一部の力のある自治体に寄付が集まるのは本意ではありません。
そこで、総務省は、返礼品の価値を寄付金額の3割前後の地元の特産品にするようにと、全国の自治体へ通知しました。
しかし、既に寄付金を獲得している一部の自治体が通知に反発したため、総務省は2018年7月6日に従わない12の自治体を名指ししました。
12の自治体は以下の通りです。

このサイトでも、還元率が高い返礼品として、これらの自治体のものを紹介しています。
先ほどの「佐賀牛切り落とし」も佐賀県嬉野市ですよね。
今後、これらの自治体の返礼品が、総務省によって強制的に廃止させられるかもしれないと言われています。
これが③行政の指導です。
これらの原因でお得な返礼品はなくなってしまうかもしれないのは、私たち一般のユーザーにとってはデメリットでしかありません。
ですので、あまり褒められた話ではありませんが、お得な返礼品がなくなってしまう前に、お早めに寄付をすることをおすすめします。
また、12の自治体の返礼品を含むお得な返礼品は下の記事で紹介しています。
参考記事①:【年収150万円~】ふるさと納税の控除上限額と10,000円の還元率ランキング15
参考記事②:【年収200万円】ふるさと納税の控除上限額と10,000円未満の還元率ランキング7
6.ポイント制のメリットデメリット

出典:ふるさとチョイス
ポイント制とは?
ポイント制とは、自治体に寄付するとポイントをもらうことができ、そのポイントをあとで特産品と交換できるというシステムです。
ただし、各自治体ごとのポイントに互換性はありません。
ポイント制のメリット
ポイント制の大きなメリットは、お礼の品を後から頼めるという点です。
ですので、年末でバタバタしていて、落ち着て欲しい返礼品を選べないけど、期限が迫っている時などには便利でしょう。
また、上手に活用すれば、余りがちな上限額の端数まで使い切ることができます。
ポイント制のデメリット
ポイント制のデメリットは、以下の3つです。
①手続きが増えてる
②還元率があまり高くないことが多い
③ポイントにも期限がある
これらを踏まえると、年末で締め切り間近のような場合を除いて、わざわざポイント制を利用する必要はないと思います。
7.ワンストップ特例制度と確定申告のメリットデメリット

出典:さとふる
ワンストップ特例制度<確定申告
サラリーマンの手続きを簡約化するために作られたワンストップ特例ですが、
正直、確定申告より大変です。
どういうことでしょうか?
それぞれの制度のメリットデメリットをまとめた表を見れば、それがわかります。
| ワンストップ特例制度 | 確定申告 | |
| メリット | ・確定申告をしなくてもよい |
・年度末にまとめて一回だけ手続きすればよい ・寄付先の自治体に制限なし |
| デメリット |
・サラリーマンしか使えない ・寄付先の自治体は5つまで ・納税する度に会社に申告 ・納税した翌年の1月10日までに再び手続きが必要 |
・確定申告をしなければならない |
ワンストップ特例制度は、確かに確定申告をしなくても良くなっていますが、手続きの回数が大幅に増えてしまっています。
また、会社に逐一報告するのも気が重いですよね。
確定申告もそこまでめんどくさくないので、ワンストップ特例制度はおすすめできないということになります。
「それでも、ワンストップ特例制度を使いたい!」という方は、こちらを参考にしてください。
確定申告のやり方
それでは、確定申告の流れを見ていきましょう。
ワンストップ特例制度よりはマシとはいえ、
多くの方が、確定申告に対してめんどくさいというイメージを持っていると思います。
しかし、役所の手続きも電子化が進んでいるため、
確定申告は思ってよりもはるかにパパっと終わってしまうんです。
確定申告の具体的な流れを見ていきましょう。
下の表は、確定申告の手続きを3つのSTEPに分けたものです。
|
STEP1 必要なものを揃える d切ってしまえば、こっちのもんです。 (1)寄附受領証明書 返礼品と一緒に送られてくるマジ大事な紙です。届いたらすぐに他の必要なものの近くに保存しておきましょう。 (2)その年の源泉徴収票 年末頃に会社から配られるはずです。保存しておきましょう。 (3)還付金を受け取るための口座番号 自分名義のものであれば問題ありません。 (4)印鑑 私はよく失くしますが、皆さんは大丈夫ですよね?(笑) (5)マイナンバー マイナンバー通知書かマイナンバーカードをご用意ください。確定申告書に記入する欄があります。 (6)本人確認書類 マイナンバーカードをお持ちの方はそれで充分です。お持ちでない方は、免許証やパスポートなどの自分がマイナンバーの持ち主であることが確認できる書類を一つご用意ください。 (7)封筒 郵送で送ってしまった方が楽です。それ用の封筒です。 STEP2 申告書を作成する 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を開いて、後は導かれるままに金額を入力するだけで完成します。この流れについてはこちらでわかりやすく解説されています。 サラリーマンの方であれば、こちらの「カンタン確定申告」から作るとさらにパパっと終わります。 STEP3 税務署に送付する 先ほど用意した封筒に源泉徴収票、寄附証明書、申告書を入れて送付しましょう。 もちろん、税務署の窓口に直接持参することも可能です。 |
と思った方も多いのではないでしょうか?
確定申告に関してもっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
8.まとめ
ここまでデメリット、メリットを紹介してきましたが、ふるさと納税の特性を正しく理解すれば、やはり参加者も自治体にもメリットのある制度であることは間違いありません。
最後に大事なことを3つだけお伝えします。
|
・自身の上限額を知ろう ・めんどうなことはサイトに頼ろう ・のんびりした気持ちで参加しよう |
これで今日からあなたもふるさと納税マスターですね!